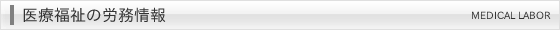今回は、遅刻した日に残業したときの残業代の考え方に関するご相談です。
当院は始業8時30分・終業18時30分(休憩2時間)で、1日の所定労働時間が8時間です。
先月、私用で1時間遅刻した職員がいます。その日に1時間30分の残業がありましたが、残業代はどのように計算すればよいでしょうか?
労働基準法では、法定労働時間を超えて実際に労働した時間(以下、実働時間)に対して、割増賃金の支払いを義務づけています。
よって、実働時間が法定労働時間である8時間を超えた30分のみ、25%以上の率で計算した割増賃金の支払いが必要となります。
ただし、就業規則等で終業時刻以降の労働に対し割増賃金を支払うと規定している場合には、その規定に従うこととなります。
 労働基準法では、使用者は、原則、1日8時間(以下、法定労働時間)を超えて労働させてはならないと定めています。
労働基準法では、使用者は、原則、1日8時間(以下、法定労働時間)を超えて労働させてはならないと定めています。
そして、法定労働時間を超えて労働させた場合、医院は、法定労働時間を超えた労働に対し割増賃金を支払わなければなりません。
この割増賃金の支払い義務は、実働時間で判断します。
今回のケースで考えると、下図のように1時間遅刻した場合、終業時刻である18時30分までの実働時間は7時間となり、19時30分までは実働時間が8時間を超えないので、割増賃金は発生しません(法定内残業)。

8時間を超える19時30分から20時までの労働に対し、割増賃金が発生します(法定外残業)。
1.にかかわらず、就業規則等で「終業時刻を超えて労働した場合に割増賃金を支給する」といった労働基準法を上回る定めをしていることがあります。この場合には、実働時間が8時間を超えていなかったとしても、終業時刻以降の労働に対して割増賃金の支払いが必要です。
今回のケースでは18時30分が終業時刻であるため、18時30分以降の労働に対し割増賃金を支払うことになります。
労働基準法の考え方をおさえた上で、就業規則等の定めを確認し、適切な割増賃金の支払いが必要です。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
- 人事労務Q&A 〜無断欠勤により連絡が取れない職員の対応〜2026/01/31
- 人事労務Q&A 〜半日単位の年次有給休暇を導入する際のポイント〜2025/12/31
- 人事労務Q&A 〜今後変わるパート職員の社会保険の加入要件〜2025/11/30
- 人事労務Q&A 〜体調不良で欠勤が続く職員に対する休職発令〜2025/10/31
- 人事労務Q&A 〜育児と仕事の両立のために柔軟な働き方を実現できるようにするための法改正〜2025/09/30
- 人事労務Q&A 〜育児休業給付金に上乗せで支給される出生後休業支援給付金〜2025/08/31
- 人事労務Q&A 〜育児短時間勤務をしたときに支給される育児時短就業給付金〜2025/07/31
- 人事労務Q&A 〜マイナンバーカードの健康保険証利用〜2025/06/30
- 人事労務Q&A 〜介護休業の対象となる家族と要介護状態の判断〜2025/05/31
- 人事労務Q&A 〜通勤手当を支給する際に考えておきたいルール〜2025/04/30
- 人事労務Q&A 〜就業規則変更手続きに必要な職員代表の適正な選出方法〜2025/03/31